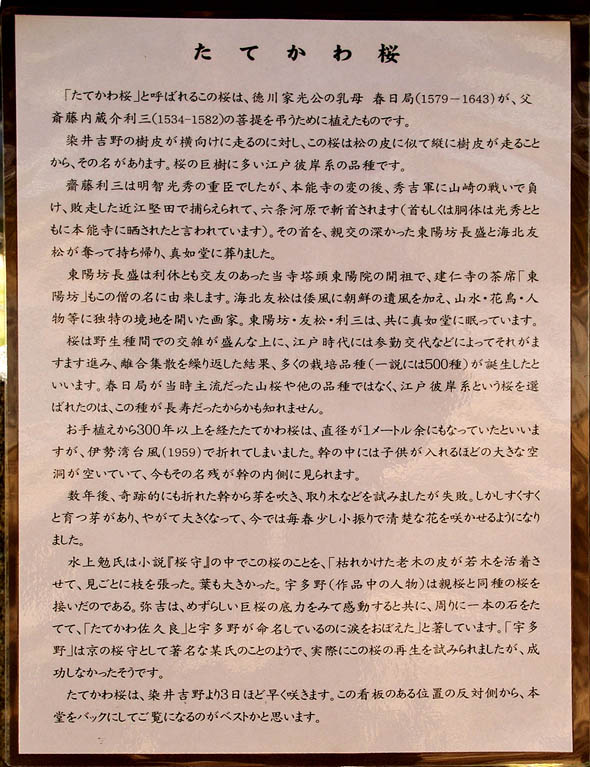縦皮(たてかわ)櫻は真如堂の本堂の南側に植えられています。
たてかわ桜の説明
▼下の文章はたてかわ桜の前に掲示されていた説明板の文をそのまま書き写しています。
たてかわ桜
「たてかわ桜」と呼ばれるこの桜は、徳川家光公の乳母 春日局(1579ー1643)が、父斎藤内蔵介利三(1534=1582)の菩提を弔うために植えたものです。
染井吉野の樹皮が横向けに走るのに対し、この桜は松の皮に似て縦に樹皮が走ることから、その名があります。桜の巨樹に多い江戸彼岸系の品種です。
齋藤利三は明智光秀の重臣でしたが、本能寺の変の後、秀吉軍に山崎の戦いで負け、敗走した近江堅田で捕らえられて、六条河原で斬首されます(首もしくは胴体は光秀とともに本能寺に晒されたと言われています)。その首を、親交の深かった東陽坊長盛と海北友松が奪って持ち帰り、真如堂に葬りました。
東陽坊長盛は利休とも交友のあった当寺塔頭東陽院の開祖で、建仁寺の茶席「東陽坊」もこの僧の名に由来します。海北友松は倭風に朝鮮の遺風を加え、山水・花鳥・人物等に独特の境地を開いた画家。東陽坊・友松・利三は、共に真如堂に眠っています。
桜は野生種間での交雑が盛んな上に、江戸時代には参勤交代などによってそれがますます進み、離合集散を繰り返した結果、多くの栽培品種(一説には500種)が誕生したといいます。春日局が当時主流だった山桜や他の品種ではなく、江戸彼岸系という桜を選ばれたのは、この種が長寿だったからかも知れません。
お手植から300年以上を経たたてかわ桜は、直径が1メートル余にもなっていたといいますが、伊勢湾台風(1959)で折れてしまいました。幹の中には子供が入れるほどの大きな空洞が空いていて、今もその名残が幹の内側に見られます。
数年後、奇跡的にも折れた幹から芽が吹き、取り木などを試みましたが失敗。しかしすくすくと育つ芽があり、やがて大きくなって、今では毎春少し小振りで清楚な花を咲かせるようになりました。
水上勉氏は小説『桜守』の中でこの桜のことを、「枯れかけた老木の皮が若木を活着させて、見ごとに枝を張った。葉も大きかった。宇多野(作品中の人物)は親桜と同種の桜を接いだのである。弥吉は、めずらしい巨桜の底力をみて感動すると共に、周りに一本の石をたてて、「たてかわ佐久良」と宇多野が命名しているのに涙をおぼえた」と著しています。「宇多野」は京の桜守として著名な某氏のことのようで、実際にこの桜の再生を試みられましたが、成功しなかったそうです。
たてかわ桜は、染井吉野より3日ほど早く咲きます。この看板のある位置の反対側から、本堂をバックにしてご覧になるのがベストかと思います。
▲上の文章はたてかわ桜の前に立ててあった説明板の文をそのまま再録しています。
秋の真如堂は紅葉がきれいです。別サイトの真如堂の桜(京都真正極楽寺)、又は真如堂の紅葉(真正極楽寺)もクリックしてください。